「国語って、どうやって勉強すればいいのか分からない」。
中学受験を見据えるご家庭の中には、そんな声をあげる方も多いのではないでしょうか。
我が家も例に漏れず、長男が国語の成績だけ停滞していて、親としても「何から手をつければいいのか」と頭を抱える日々でした。
こんにちは。40代会社員であり、2027年に中学受験を予定している長男(小5)と、長女(小1)を育てる父親です。
共働き家庭として日々の時間捻出に苦戦しつつも、我が子の成長に少しでも伴走できるように模索を続けています。
わたし自身や家族の状況についてはこちらの記事をご覧ください。
→初投稿_自己紹介
今年の1月、小学4年における全8回の公開模試の結果が出揃いました。
他教科に比べて明らかに足を引っ張っていたのが国語でした。
点数だけで言えば社会や算数は安定している一方で、国語だけが公開模試で偏差値50を下回ることもしばしば。
「本人に国語難しい?」と聞くと、「問題の意図が分からない」「選択肢を選べない」「記述が書けない」とつまずいてしまう――。
気持ちは分かるし、具体的な解決方法が見つからないまま、2月から小5のカリキュラムがスタート。
この記事では、国語の成績を少しでも上げようと5ヶ月間試行錯誤してきた経過を綴ります。
「育成テスト」と「ふくしま式」の活用法を中心に、公開模試の偏差値を47→56に伸ばした過程を詳しくご紹介します。
お子さんの国語対策に悩むご家庭にとって、少しでも参考になれば幸いです。
育成テストを使った「予測力」の養成
「育成テスト」は、日能研で2週間に1回行われる確認テストです。
通常の授業で扱った内容が中心ですが、文章読解における出題傾向に“型”があることに着目し、我が家ではChatGPTを活用して毎週オリジナル問題を作成していました。
具体的には、各回の狙いをChatGPTに読み込ませ、そこから“問われそうな設問”をいくつか予想して出題させるという方法です。
このアプローチにより、長男は文章に対する読解の“構え”を持てるようになり、「この文章はどこが聞かれそうか」「設問の意図は何か」を考える習慣が身につき始めている気がします。
最初は親が横について解説していましたが、2か月後には自力で選択肢の根拠を説明できるようになっており、成長を実感することができました。
ふくしま式で「言語化する力」を養う
もう一つの武器が、「ふくしま式『本当の国語力』が身につく問題集(小学生版ベーシック)」。
ふくしま式の教材はこちらで詳細が確認できます:
ふくしま国語塾
これは、ただ設問に答えるのではなく、設問の構造・選択肢の根拠・正解の導き方を“言語化する力”を育ててくれる教材です。
特に「意味段落をつかむ力」や「文脈に合う言い換え力」は、長男のように感覚で国語を解こうとしていた子にぴったりでした。
この教材を使う際に意識したのは「親子での対話」。
子どもが答えた後、「どうしてそれを選んだの?」「他の選択肢はどうだった?」と問いかけることで、考える力と答える力が同時に育っていきました。
こうした丁寧なプロセスが、「記述問題」における“理由づけ”にも活かされ、公開模試でも徐々に成果が出始めました。
少しずつ変わる子どもの姿
長男の場合は、勉強に限りませんが性格的に間違えることに恐怖に近い拒否感があり、予定や想定されていることで安心感につながり、安定する傾向にあります。
設問の聞き方、形式など事前に経験しておくことで、授業で習った範囲で解答できるはずだという自信に繋がったのかなぁと想像しています。
また、記述問題は慣れと反復練習によって何もかけず空欄のまま試験を終えることがなくなってきたのかなと見受けています。
成果とこれから
結果として、2025年3月からの取り組みで、国語の成績は明らかに右肩上がりになりました。
4年生の時は1度も150点満点中100点を超えることがありませんでした。
(本人はよく冗談で国語だけ100点満点だったよと言っていましたw)
それが5年生の公開模試では4月以降、全て100点を超えて偏差値が55前後で安定してきました。
これは、感覚的に読むのではなく、「設問から逆算する」姿勢を持てるようになったことが大きいと感じています。
すぐに実行できる3つの方法
- 毎週の文章問題から“出されそうな設問”を自分で作ってみる(もしくはChatGPTで生成)
- 「なぜこの答えになるのか?」を言語化する習慣を持つ
- ふくしま式のように、構造的な読み解きを教えてくれる教材を導入する
国語は目に見えづらく、成果が出るまで時間がかかる教科だと思っています。
小さな成功体験を積み上げた先に受験対策に関係なく、読書を好きになり、言葉の持つ力を感じられるセンスにつながれば親としてこれほど嬉しいことはありません。
そしてそれは、受験を超えて「生きる力」にもなっていくと信じています。
まとめ
今回ご紹介した勉強法は、中学受験の素人であるわたしが根拠もなく思いつきで始めたものです。
とはいえ、子どもと最も身近で接してきた親だからこそ始められたことでもありました。
育成テストとふくしま式の組み合わせは、子どもの理解を深め、かつ「答えの根拠を言語化する」力を育てるうえでとても相性が良かったと実感しています。
国語でつまずいているお子さんがいらっしゃる方なら、まずは「なぜつまずいているのか」を一緒に言語化してみると打開策のヒントが見つかるかもしれません。
国語は「なんとなく」では伸びないと私は考えています。
しかし、「わかった」を積み重ねていくと、ある日突然、景色が変わる瞬間があります。
私たち親子はその体験を通じて、国語という教科に新しい希望を見出すことができました。
親も子も悩みながら試行錯誤していくその時間が、何より大切な学びの時間だったと、今では心から思えます。

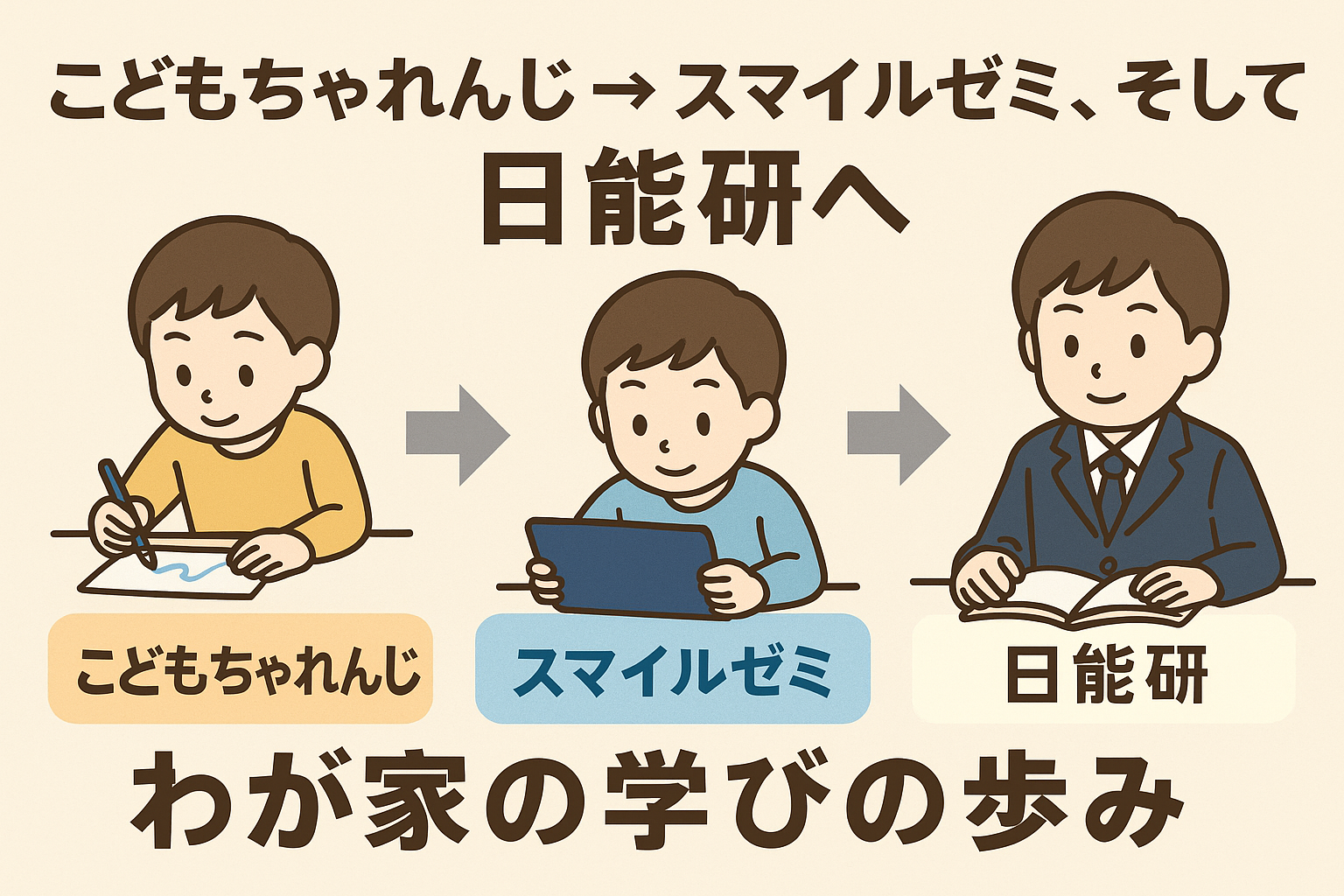
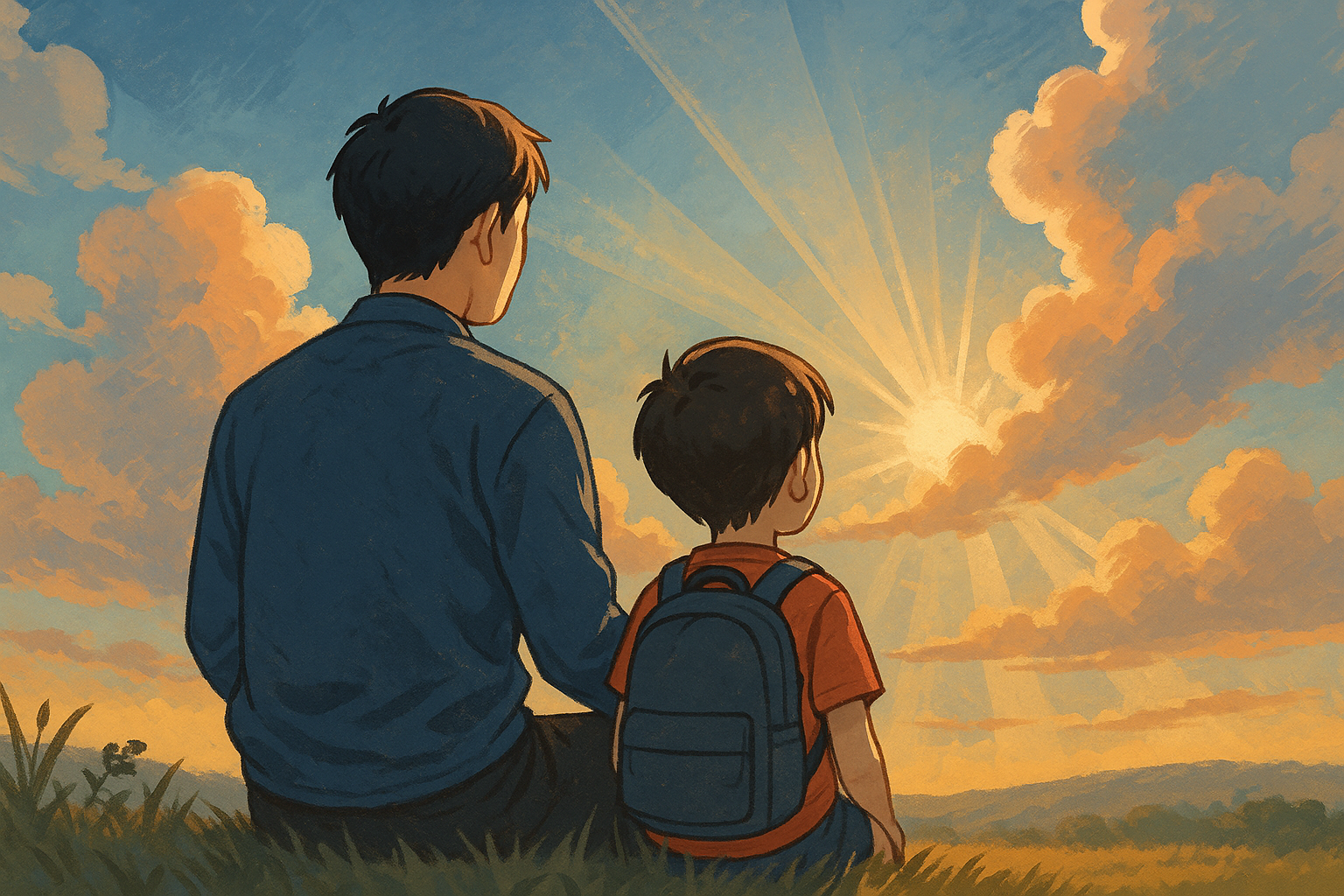
コメント