わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
まだ志望校が固まっていなくても「行く価値」はある

小5の秋。偏差値表だけを眺めていても、親子の温度差は埋まりません。そこで私は、学校名や日付を特定しない範囲で、とある都内私立中の説明会に参加しました(平日午前/所要約80分)。参加してまず分かったのは、現場でしか得られない手触りの情報が多いということです。校長・教頭・教科担当の先生が登壇し、広報が進行。教育方針だけでなく、校内の空気感や生徒の立ち居振る舞いまで見えてきました。
「いま志望が固まっていなくても遅くない?」「6年からではだめ?」と迷う方は多いはずです。結論から言うと、小5秋は“観察の季節”。決断ではなく仮説づくりのために足を運ぶ価値が十分にあります。
体験の共有:保護者が見た3つの“リアル”

(1)入学後の学習像を、学校が“明確に期待値”として示す
登壇者の話からは、大学附属ならではの強みと同時に、「入ってからもしっかり勉強する学校」という明確なメッセージが伝わりました。唯一の直営附属という誇りと責任から、一般入試組に引けを取らない、むしろ牽引する学力を育てる設計であると感じます。例えば推薦基準に英検2級を掲げることも、一定以上の学力を前提とした育成方針の表れに見えました。資料にも宿題は「多め」と明記。“居心地のよさ”と“学びの厳しさ”の両立がキーワードだと理解しました。
(2)広報の工夫が進化:月ごとに趣向を変えた説明会設計
同校は秋に複数回の説明会を実施していましたが、内容は同一ではありません。月をまたぐと、中1・中2生徒の生活紹介や、入試の出題方針・注意点の先出しなど、回ごとに角度を変えてくる構成。11月には直近の過去問を題材にした「入試対策説明会」も予定され、“広報=志望動機の醸成”という視点が徹底されていると感じました。
(3)校内見学で“日常の秩序”が見える
説明会後は自由見学。授業中の立ち歩き・私語がほぼ見られず、学習に集中できる環境が整っていると実感しました。昼休みはお弁当持参/学食利用/弁当販売と選択肢が複数。図書館は都内上位の蔵書規模と説明があり、学習資源の豊かさも魅力的でした。広報担当者の「母校愛が強い生徒が多い」という言葉とも整合的で、“好き”が継続学習の土台になっている印象です。
読者への問い:あなたのご家庭に当てはめるなら?
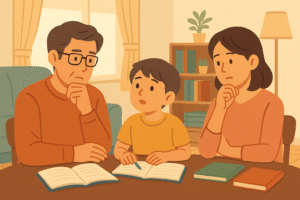
- 学校に“居場所”を感じられるか。厳しさと温かさのバランスはどうか。
- 学習負荷(宿題量・検定基準)と、家庭のリズムは噛み合うか。
- 広報イベントの作り込みから、学校の情報発信力やコミュニケーション文化は見えたか。
- 図書館や学食、休み時間の雰囲気など、学力以外の学習資本をどう評価するか。
数字や偏差値で比較しづらい部分ほど、現地での一次情報が効きます。説明会は「合う/合わない」の仮説を磨く場。スライドよりも、登壇者の言葉の温度・校内の空気・生徒の目線を手帳に残すのがおすすめです。
一次情報:参加当日の観察メモ(抜粋)
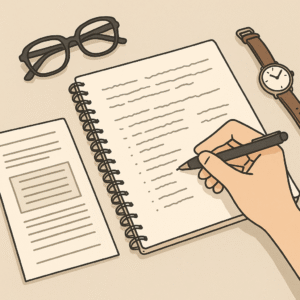
- 実施時間:約80分(校長・教頭・教科担当が登壇、広報が司会)
- 参加規模:会場キャパ600に対し実参加は約100(平日午前のため分散か)
- 参加者の層:母1人参加が最多/夫婦参加は約1割/親子参加は約2割
- 服装:指定なし。全体にカジュアル寄り(Tシャツ層も)
- 学習方針:宿題は多め。英検2級を推薦基準に掲示。附属の“強みと責任”を強調
- 入試情報(傾向):合格者平均−受験者平均の差は算数が最も大きい(約16〜18点)。他教科は5〜9点
- 個別相談:説明会後に予約不要の40分枠あり(希望者)
- 校内資源:蔵書は都内上位規模の図書館。自学の環境が豊富
数字で見える強み(算数の差がつきやすい等)と、数字では見えない強み(母校愛・落ち着いた学習文化)の双方が確認できました。偏差値表には載らない“校風の質”が判断の決め手になり得ます。
よくある誤解と、今回の示唆
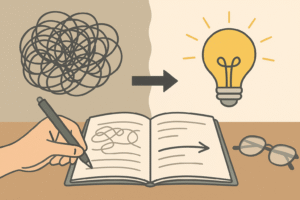
「同一校の説明会は内容が同じ」→ いいえ、月で角度が変わる
秋に複数回ある説明会は、同一内容とは限りません。生徒発表が入る回、入試方針を深掘りする回など、設計が異なります。可能なら2回以上を見比べると、学校理解の解像度が一段上がります。
「附属=勉強ゆるめ」→ いいえ、むしろ“育成の責任”が重い
附属だから安心、は半分正解で半分誤解。大学直結の責任感から、推薦基準や宿題量で一定の負荷を設計しているケースがあります。“保護的×挑戦的”のバランスを、現地で確かめたいところです。
「偏差値表だけで比較できる」→ いいえ、現場の秩序も評価軸
授業・昼休みの秩序、図書館の使われ方、先生方の言葉の温度は、学力の土台を支える“学習文化”です。ここは資料で伝わりにくく、現地観察が最短でした。
明日からできる3アクション
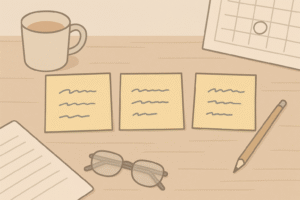
- 候補校の説明会を月別に1校ずつ予約(同校で2回見る価値あり)。
- 観察メモのテンプレを準備(登壇者の要点/学習負荷の目安/校内の秩序/資源)。
- 家庭内ミニ会議(10分)で“合う/合わない”の仮説を更新。
説明会は「決断の場」ではなく、家庭の意思決定を前に進める情報収集の場です。無理のない頻度で、しかし粘り強く。小5秋の一歩が、小6の迷いを減らします。
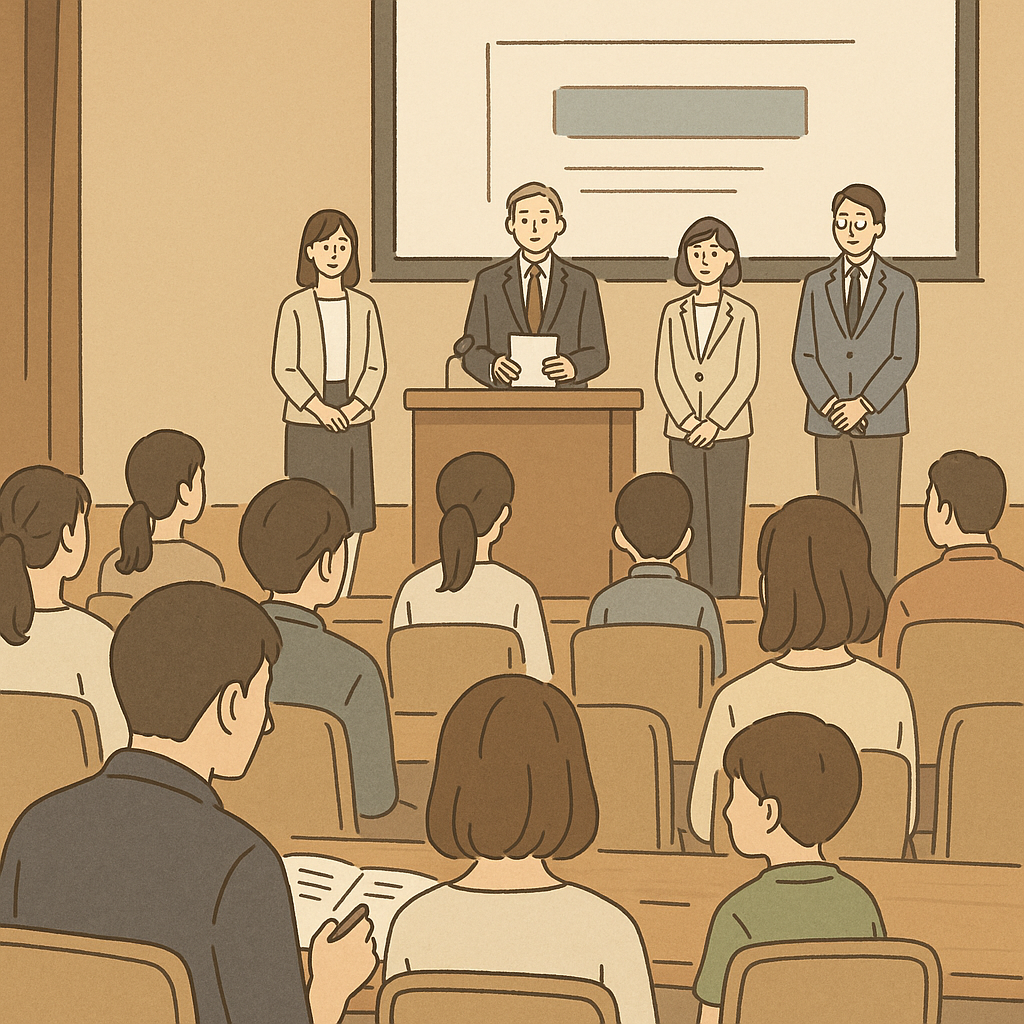


コメント