わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
小5秋はなぜ重要か

小学校5年生の秋は、中学受験に向けて「学習の本格化」と「応用力養成」が始まる重要な時期です。春から積み重ねてきた基礎の理解が十分であれば、この時期の伸びは顕著に現れます。逆に基礎が不十分なまま応用期に突入すると、問題のレベルが一気に上がるため「どこまで分かっているか、どこから分からないか」が曖昧になりやすく、伸び悩みにつながります。
また、この時期は模試やテストの頻度が増えます。自分の学力を客観的に把握できる機会が増えるため、志望校の方向性を具体化する材料としても大きな意味を持ちます。
学習の本格化と算数の壁
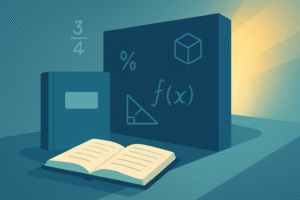
塾では小5秋から主要単元の基本を終え、一段高いレベルの内容に入ります。算数では速さや割合、比といった単元を本格的に扱い始め、論理的思考や問題解決力が求められる場面が増えます。
実際に、9月1日の後期最初の授業で、わが家の長男は「パパって小学5年生のとき算数でどんなことを勉強したの?」と尋ねてきました。おそらく授業で新しいテーマを聞いたものの、全体像がつかめず不安を抱いたのでしょう。彼の性格を考えると「全体像が見えないと足が止まる」タイプであり、秋の算数が難所とされる理由を体感した瞬間でした。
こうした時期には、親が「何を、どこまでやるか」を見通しとして共有してあげるだけでも安心感につながります。
国語の宿題で見えた弱点克服のヒント
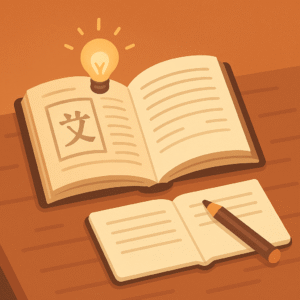
国語では宿題として「漢字の部首名を答える」という課題が出ました。しかし授業でも扱わず、テキストにも記載がなく、長男は「どうやって調べればいいのか分からない」と二の足を踏んでいました。
ここで私は電子辞書の漢字辞典を一緒に開き、部首名が必ず載っていることを教えました。すると、長男の表情は一変しました。さらに「読み方が難しいものはパパに聞いていいよ」と伝えると安心した様子で、集中力を取り戻しました。その後、約1時間で宿題をすべてやり切ったのです。
この体験は「調べれば解決できる」「分からなければ聞いていい」という学びにつながり、弱点克服の第一歩となりました。
【関連記事】国語が苦手な小5|共働き世帯の父親が試行錯誤した足跡
家庭でできる弱点克服の具体策

- 間違いの記録と分析:解けなかった問題や分からなかった単元をノートに記録し、「なぜ間違えたのか」を言語化して分析する習慣をつけます。
- 基礎基本の反復練習:応用問題に取り組む前に、基礎を繰り返すことで理解を盤石にします。「できる問題をもう一度解く」ことが自信につながります。
- 単元別教材の活用:苦手単元を扱う薄めの教材を用意し、少しずつ確実に進めることで「できる」に変えていきます。
- アウトプットで確認:学習後に「今日は何を学んだの?」と尋ね、子どもに説明させることで理解度を再確認できます。
- 前向きな声かけ:結果だけでなく努力を認め、「昨日より集中できたね」と具体的に褒めることが意欲の持続につながります。
親の役割と関わり方

- 短期の目標を設定する:「次のテストで5点アップしよう」など、達成可能な小さな目標を共有する。
- 失敗を肯定的に受け止める:「間違えても次につなげれば大丈夫」と安心感を与える。
- 寄り添って見守る:「いつでも味方」というスタンスで接することで挑戦意欲を支える。
過干渉にならずに観察者の立場で関わることが、子どもの自主性を伸ばし、継続的な成長を後押しします。
【関連記事】パパは毎日5分でOK:成績が上がった声かけ・チェック5選
小6への架け橋としての小5秋

小6になると、過去問演習や志望校別対策が始まり、学習量も一気に増えます。小5秋はそのための「橋渡し」の時期です。基礎の定着と応用力の芽を育てておくことで、小6の学習をスムーズにスタートできます。
算数の新単元への不安や国語の宿題でのつまずきは、一見すると小さな出来事に思えます。しかし、それをどう乗り越えるかが、次の大きな学習の礎になります。
まとめ
小5秋は「学習の本格化期」であり、基礎の徹底と応用への準備が大切です。弱点克服には「記録・反復・アウトプット」、親の役割は「目標設定・声かけ・見守り」が効果を発揮します。
長男との算数や国語の小さなエピソードからも分かるように、子どもは適切なサポートと小さな成功体験を通じて確実に成長していきます。親が寄り添いながら環境を整え、安心して挑戦できる雰囲気をつくることが、秋以降の学びの伸びに直結します。

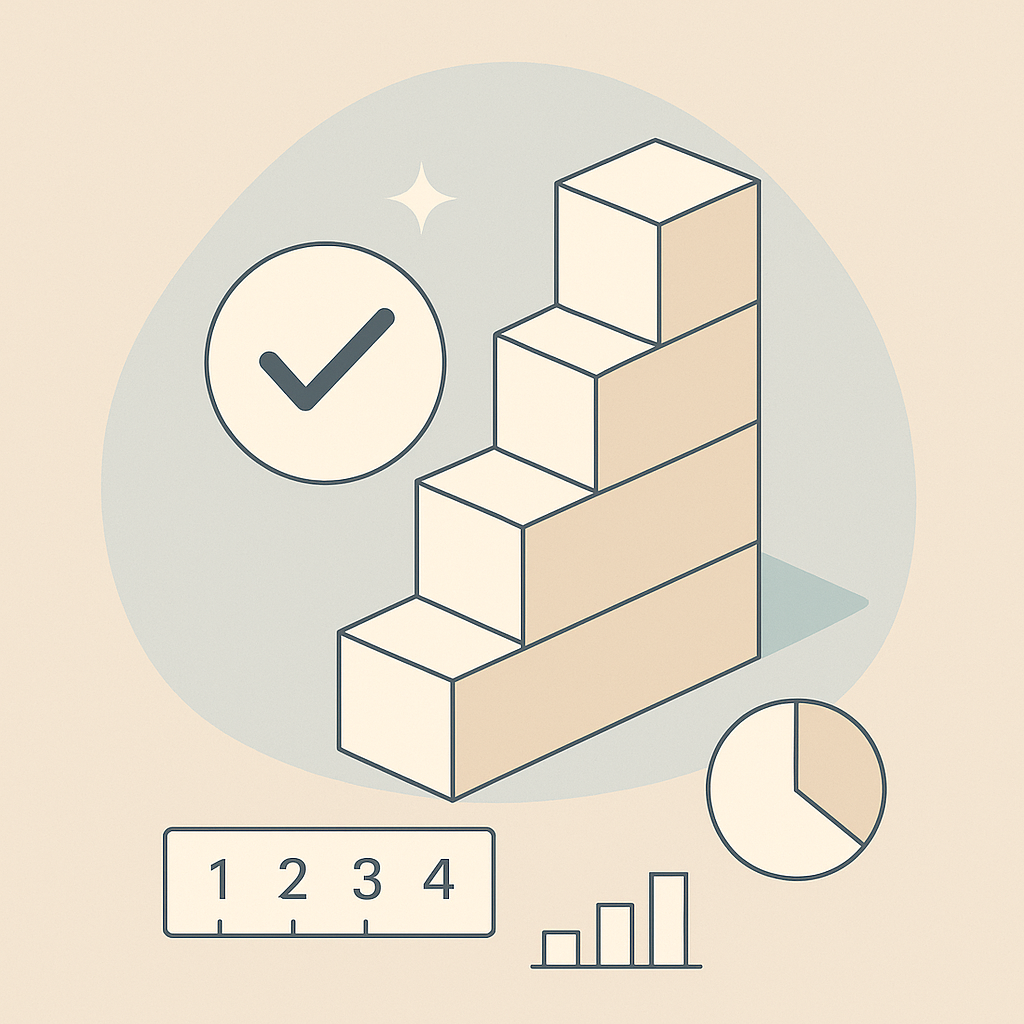
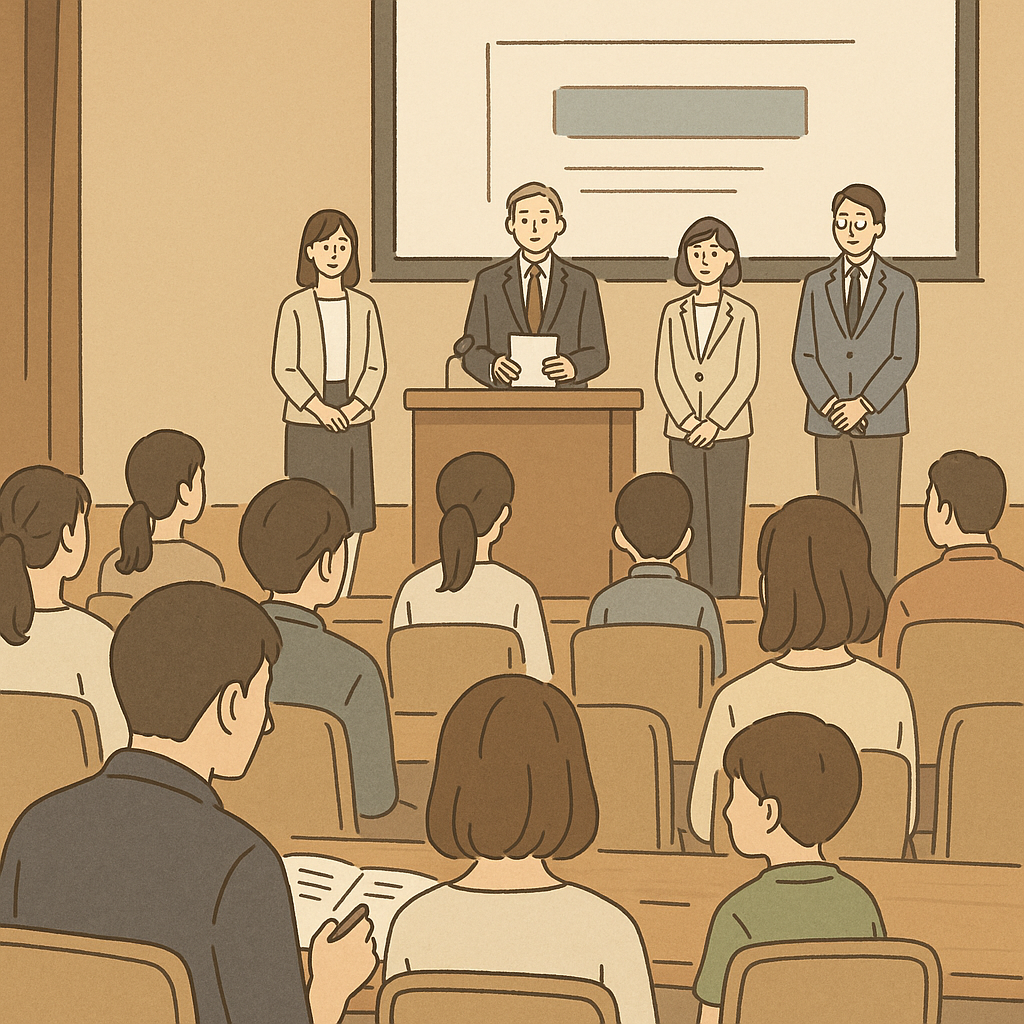
コメント