わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
志望校選び、本格スタートの合図

「そろそろ志望校を具体的に考えましょう」——5年生の秋に日能研が開催する志望校選定保護者会に参加して、最初に突きつけられたのはこのメッセージでした。
会場に集まった保護者たちは、皆一様に少し緊張した面持ちで資料に目を通していました。
わが家も「まだ先の話」と思っていたのですが、配布された分厚い資料をめくるうちに、志望校選びが決して早すぎることではないと実感しました。
会場の空気と印象に残った言葉

当日のプログラムは約90分。冒頭では受験環境の変化について、日能研の先生が最新データを交えながら語ってくれました。
「首都圏の中学受験率はすでに27%を超えています。4人に1人が受験をする時代です」という言葉に、改めて競争環境の厳しさを感じました。
また、「偏差値だけで学校を選ぶと、入学後に親子でミスマッチに悩むケースが増えています」との指摘も強く印象に残りました。
資料に示された“共通の地図”

- 5年生の秋までに第一志望・チャレンジ校を見据える
- 6年生の夏までに併願校の候補を固める
- 12月までに全受験校を決定し出願準備を開始する
この「ロードマップ」は、保護者にとってまさに地図のような存在です。
今の時期から模試や学校説明会をどう活用するかを逆算できるため、漫然と過ごすのとでは大きな差がつくと感じました。
偏差値だけでは見えない“校風”

資料の中で特に目を引いたのは「学校選びのモノサシ」に関するページでした。
通学時間や男女校・共学校の別、制服や部活動といった条件だけでなく、「学校の教育内容や校風を体感すること」が強調されていたのです。例えば、
- 教育DX(1人1台端末、デジタル教科書の導入)
- 探究学習やキャリア教育の実践度
- 大学附属校なら内部進学の実態
これらは国の教育政策として全国的に進んでいる取り組みと、学校独自の特色が入り混じる領域です。説明会で語られる内容が「全国的に共通する施策」なのか、「その学校ならではの工夫」なのかを見極める視点が必要だと改めて気づきました。
最新の入試トレンドと学校の個性

- 偏差値40〜50台の学校でも、学習習慣の定着や面倒見の良さで人気が上昇している
- 投資教育やデータサイエンスコースなど、新しいカリキュラムを打ち出す学校が増えている
- 地方寮制中学が東京会場で入試を行い、広域から受験生を集めている
こうした動きは「難関校かどうか」だけでは測れない、学校ごとの魅力を示しています。
説明会に足を運んで初めて知る情報も多く、現場で体感する大切さを実感しました。
学費と進路の“リアル”
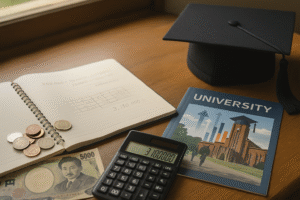
学費や進学実績についても具体的な数字が提示されていました。
首都圏私立中高一貫校の6年間総額は500万円台〜800万円台が中心で、公立に比べれば負担は重くなります。
一方で、内部進学率が高い学校や、探究・海外大学進学サポートに力を入れる学校もあり、「コストに見合う教育価値があるか」を家庭ごとに判断する必要があると感じました。
進路面では、東大合格実績に注目が集まりがちですが、「大学附属校での内部進学」という選択肢が現実的であることも強調されていました。
保護者に投げかけられた問い
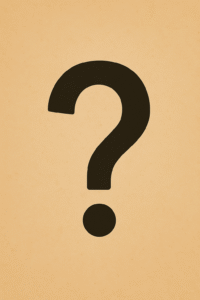
講演の最後に、日能研の先生から投げかけられた問いがあります。
「あなたのご家庭では、どんな人間像を育てたいのか」。
合格実績や偏差値に気を取られがちですが、6年間を通して「どんな子に育ってほしいのか」を明確にしておかないと、志望校の選定はブレてしまう。保護者として、わが家の教育観を言語化しておく必要性を痛感しました。
今後に向けて:使い倒す3ステップ

- 資料を家庭のモノサシに重ねる — 配布資料を眺めるだけでなく、わが家の価値観や条件に照らして整理する。
- 説明会や模試で“質問”を投げる — 国の制度か学校独自かを切り分ける質問を準備することで、より深い理解につながる。
- 家庭のビジョンを言語化する — 「どんな6年間を送りたいか」を夫婦で話し合い、子どもとも共有しておく。
まとめ:受け身から主体的へ
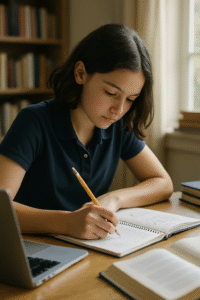
今回の日能研保護者会は、単なる情報提供の場ではなく、家庭の教育方針を問い直すきっかけとなりました。
学校説明会や模試は「受け身で情報を受け取る場」ではなく、「家庭のモノサシで学校の姿を測る場」に変えることができるのだと思います。
次回以降の説明会に参加する際は、今回の学びを活かして、より主体的に「わが家らしい学校選び」を進めたいと感じています。



コメント