わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
夏休みは全49日間でした。わが家の小5は、そのうち約半分を講習・テスト・特別講座で過ごしました。一方で、学びだけに偏らず、家族の時間もきちんと確保できた夏だったと実感しています。この記事では、通塾日数・学習時間・費用を数字で可視化し、手応えと課題、そして9月以降の運用案までまとめます。
サマリー:3行でわかる今夏
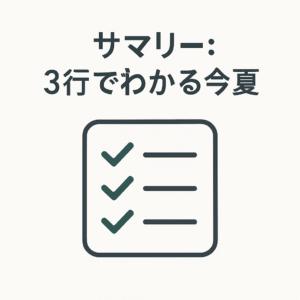
- 通塾24日(講習18・テスト3・特別講座3)で計93コマ/104.5時間(休憩含む)
- 費用148,500円(講習132,660円+特別講座15,840円)
- 家族行事も十分に確保(1泊2日旅行、帰省3泊4日、北海道3泊4日)
通塾スケジュール:24日をどう配分したか
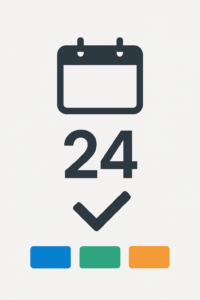
- 講習18日:連続する週は負荷が高め、間に「完全休養日」を挟むと回復が早いと感じました。
- テスト3日:特別テストを軸に1週間の学習配分を見直し、復習の起点にしました。
- 特別講座3日:弱点領域の底上げに活用しました。
なお、夏期講習の授業は4コマ・5時間10分(休憩含む)と長丁場でした。直近で通常授業が再開し、2コマ・2時間30分(休憩含む)に戻ったところ、子どもの第一声は「授業が短く感じた」でした。長期の高負荷を経て、通常運転が相対的に軽く感じられるのは、次学期のリズムづくりにプラスだと受け止めています。
学習の量:93コマ/104.5時間の内訳

- 授業コマ数:93コマ(講義・演習・確認テストなどを含む)
- 学習時間:合計104.5時間(校舎内の休憩時間を含む)
- 特別テスト:3回(学習のペースメーカーとして機能)
量の面では十分に積み上げられました。一方で、「翌日に残る理解」=質の点では、教科ごとにムラが出やすく、復習設計をもう一歩具体化する必要を感じました。
費用の内訳:合計148,500円
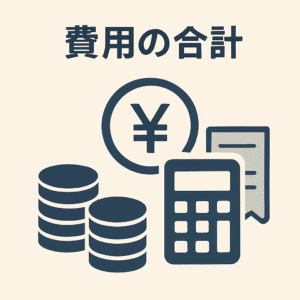
- 夏期講習代:132,660円
- 特別講座代:15,840円
- 合計:148,500円
費用は「量(出席)×質(到達)」の掛け算で評価するつもりです。支出の妥当性は、テスト→復習→定着の循環が回ったかどうかで検証します。
手応えと課題:どこが伸びて、どこに壁があるか
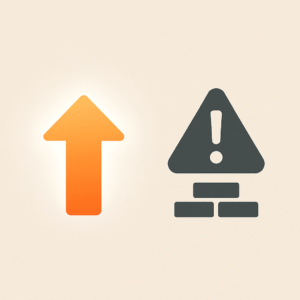
手応えのあった点
- 学習体力:長時間座る抵抗感が薄れ、通常授業が「短く」感じられるほどに持久力がつきました。
- テスト運用:特別テストを起点とした1週間設計(予習→演習→復習)が、一定程度機能しました。
見えた課題
- 国語:漢字の取りこぼし(量の繰り返しだけでは定着しない)。記述は無答が減少した一方で、主語述語の不一致や根拠の薄さが残存。
- 社会:知識問題はおおむね対応可。資料読み取り(地図・グラフ)で手が止まりやすい。
- 理科:用語の意味づけが甘い単元で躓きがち。図の読み取りと因果の言語化が課題。
家族時間:学びと両立できた理由
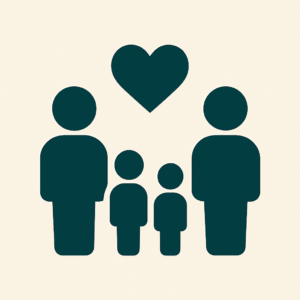
「家族の時間が削られた」という感覚はありませんでした。実際には、1泊2日(大阪万博・京都太秦)の小旅行(祖父母・叔父と同行)、3泊4日の帰省、3泊4日の北海道旅行を実施しました。長男は2日前倒しで夏休みに入っていたことも功を奏し、学びの密度を確保しながら非認知面(段取り・耐性・切替)の体験も積めました。
9月以降の運用:量から「回る仕組み」へ
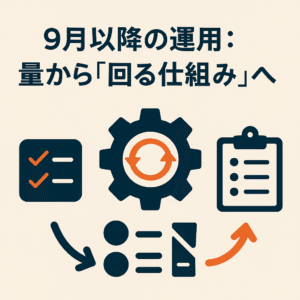
① 平日ミニ学習(10〜15分)を固定化
- 国語:5分要約+語彙ミニカード(主語・述語を意識した1文づくり)
- 社会:白地図1枚+グラフ1本の「見る→言う→書く」ミニセット
- 理科:用語1テーマの「図に矢印で因果を書く」練習
② 週末の「復習デー」を1本化
- 特別テストの誤答から再発防止カードを1枚だけ作成(原因→対策→合図)。
- 翌週の起点予約(付箋1枚)で「どこから始めるか」を明文化。
③ 観察ログでムダ打ちを減らす
- 「座ってから鉛筆が動くまでの秒数」「最初に止まる場所(文・図・設問)」を親が1行記録。
- 評価語は使わず事実だけ。処方箋は次週に回す前提で、観察を続けます。
まとめ:数字で確かめ、仕組みで積み上げる
この夏は24日/93コマ/104.5時間/148,500円という数字で振り返ることができました。
十分な量を投下した一方で、次は「回る仕組み」に磨きをかけます。
ミニ学習の固定化、週末の再発防止カード、観察ログの3本柱で、9月以降は“量の反復”から“再現性のある定着”へ重心を移していきます。
家庭の時間を守りながら学びを前に進めることは可能です。数字で現状を見える化し、小さな仕組みを積み上げていけば、次のテストは「点の増減」だけでなく、学びの手触りから変わっていくはずです。
https://www.nichinoken.co.jp
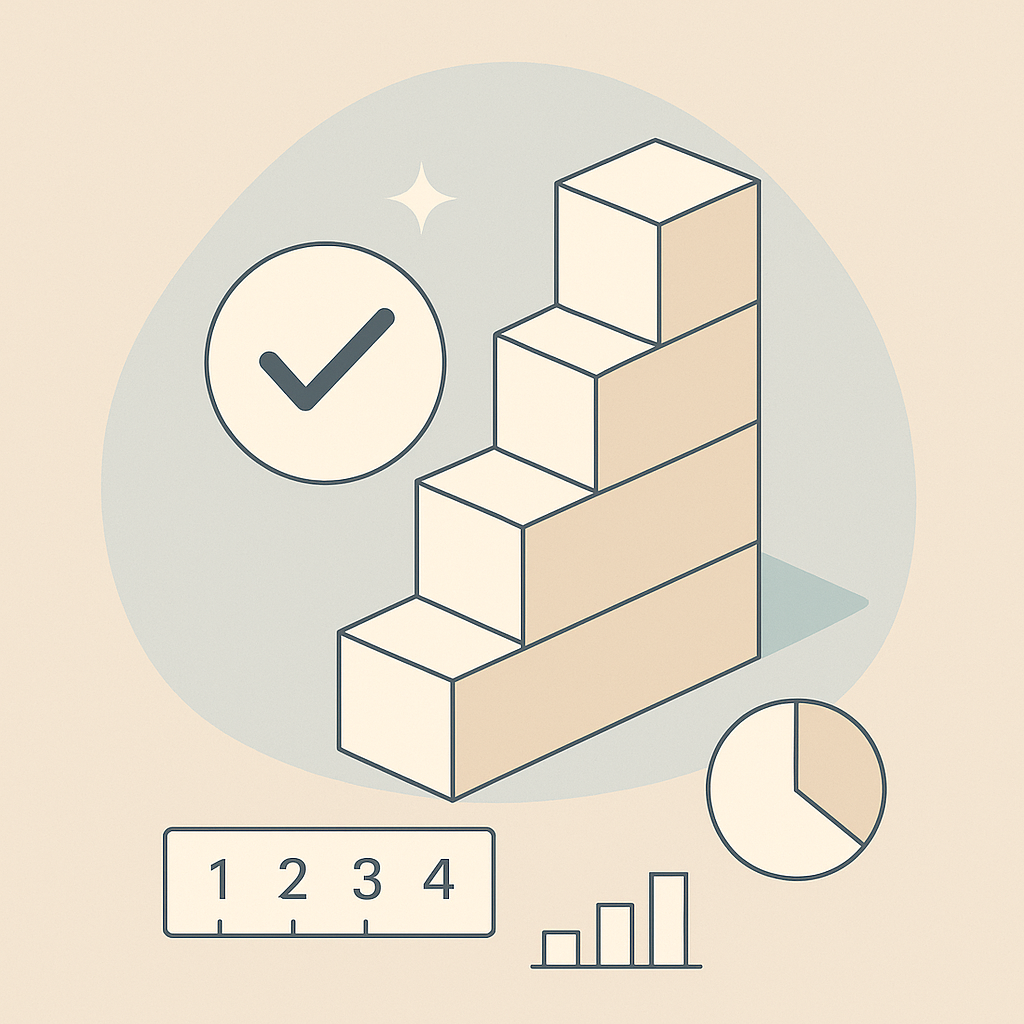


コメント