わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
説明会の価値は“聞き方”で何倍にもなる

学校説明会は、参加するだけでも雰囲気や校風を知る手がかりになります。とはいえ、同じ60〜90分でも「受け取る情報の質と量」は大きく差が出ます。鍵は、国の教育行政で“全国共通に進むこと”と、学校が“独自に磨いていること”を分けて聞き、後者=差別化ポイントを見極めることです。この記事ではそのための土台(制度整理)と、現場で使える質問ベスト10をセットでお届けします。
同じ説明でも、質問次第で「見える景色」が変わる

複数校の説明会に参加して分かったのは、登壇内容の一定部分はどこも似ていることです(ICT整備、探究学習、英語4技能など)。一方で、質問すると学校ごとの運用差、評価の仕方、内部進学の条件、フィードバック速度、学外連携の濃度など“生活と学びのリアル”が開示されます。つまり、受け身だと同質化された情報に終わり、能動的に聞けば意思決定の材料が揃います。
60秒で押さえる教育行政のトレンド

教育DX(1人1台・デジタル教科書・生成AI)
- 端末は更新期に入り、校務・学習データを“つなぐ”方針が強化。英語はデジタル教科書が本格導入、算数・数学ほかも拡大中。
- 生成AIは国の指針を前提に「活用ルール+情報モラル」で運用。自治体・学校ごとに導入の濃淡あり。
学費・進学支援(高校・大学)
- 高校授業料は国+自治体の支援で“実質無償化”エリアが拡大。私立でも負担が軽くなる地域が増加。
- 大学では修学支援新制度に加え、2025年度から多子世帯の授業料・入学金の大幅減免が実施。
理工・データ人材育成(SSH/DXハイスクール等)
- 指定校は探究・大学連携・発表の「量と質」をKPIで開示。非指定校でも独自プログラムの強化例あり。
学習指導要領の次期改訂議論
- 探究・情報教育の一貫強化、デジタル活用、評価の多面化などが論点。実施は段階的見込み。
この「共通トレンド」を頭に入れておくと、説明会で語られる内容が“全国的に当然の整備”なのか、“その学校ならではの強み”なのかを瞬時に仕分けできるようになります。
核心に届く質問ベスト10
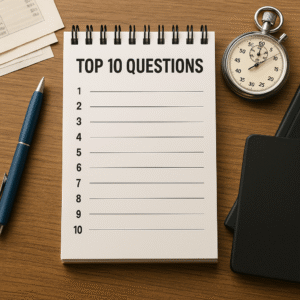
- 内部進学の実態は?(学部学科別の進学率、必要評定・行動要件、学部変更の可否と実績)
意図:“安心”の条件とリスク分岐を前もって把握。 - 端末購入・更新と家庭負担、欠席時の学習代替は?(機種・買替サイクル、故障時の予備、オンライン振替の可否)
意図:タイパと学びの継続性を左右する運用の肝。 - デジタル教科書と学習eポータルの運用は?(対象教科、提出・返却、保護者の閲覧権限)
意図:“返却速度”と“見える化”が学びのPDCAを決める。 - 生成AIの校内ルールと授業実例は?(出典明記・検証・倫理の指導、提出物での扱い)
意図:時流対応を“学力”に変えているかを確認。 - SSHやDXハイスクール指定の有無と成果KPIは?(大学連携件数、生徒発表数、入賞実績)
意図:看板だけでなく、量と質の“結果”で見る。 - 理工・データ系を伸ばす具体策は?(情報I/II・統計・プログラミングの体制、外部コンテスト支援)
意図:“実践の場”と指導の手厚さを見極め。 - 国語が弱めな生徒への支援は?(少人数補習、記述ルーブリック、返却スピード、横断的言語活動)
意図:学力のボトルネックに対する学校の処方箋。 - 宿題量・定期テスト・自習室・部活の両立モデルは?(1週間の標準行動、テスト前の支援)
意図:日々の“回し方”が現実的かをチェック。 - 進路指導の出口データは?(GPA分布、内部進学と外部合格の内訳、英検・留学枠)
意図:“出口の強さ”と多様な進路の実在。 - 学費の総額と追加費用、将来の値上げ方針は?(施設・ICT・指定品・研修・遠征、分納・奨学金)
意図:授業料以外を含む“総コスト”の把握。
+20秒で効く追い質問テンプレ
- 「昨年度と今年度の数値(率・件数)を教えてください」→ 実績比較で“言い切り”を検証。
- 「上位10%の生徒は1週間でどのくらい勉強・活動しますか」→ 具体的な行動モデルを把握。
- 「返却までの平均日数は?」→ 学びのPDCA速度を数値で確認。
- 「保護者が見られる画面を実際に見せてください」→ eポータルの実物で運用をチェック。
見えたら“良いサイン”、要注意サイン

良いサイン
- データと証拠(資料・QR)が即出る。割合は必ず母数つき。
- 失敗例と改善策を具体に語る(安全・倫理・再挑戦の仕組み)。
- 提出・返却の運用が明確(期日・ルーブリック・返却速度)。
要注意サイン
- 「検討中」「これから」が多く、現場の運用例が示されない。
- “看板”は強いが、KPIや実績の数値が出てこない。
- 学費は授業料だけ説明し、周辺費用が見積り提示されない。
使い倒す3ステップ
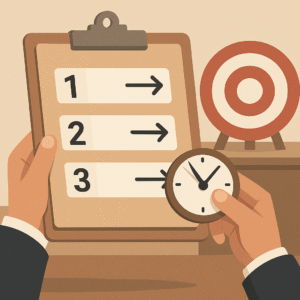
- 1枚メモを作る(制度整理の要点+質問ベスト10+追い質問)。
- “数値で答えてほしい箇所”に★印(進学率、返却日数、連携件数、学費総額)。
- 家族ミニ会議(通学時間、部活、学費の優先順位)で“何を比べるか”を決める。
説明会は「情報を受け取る場」から「学校の本気度を確かめる場」へ。制度整理という地図を持ち、質問というコンパスで歩けば、校風の相性も、学びの質も、費用感も、具体の言葉と数字で見えてきます。次の1校は、このリストを手元に参加してみてください。

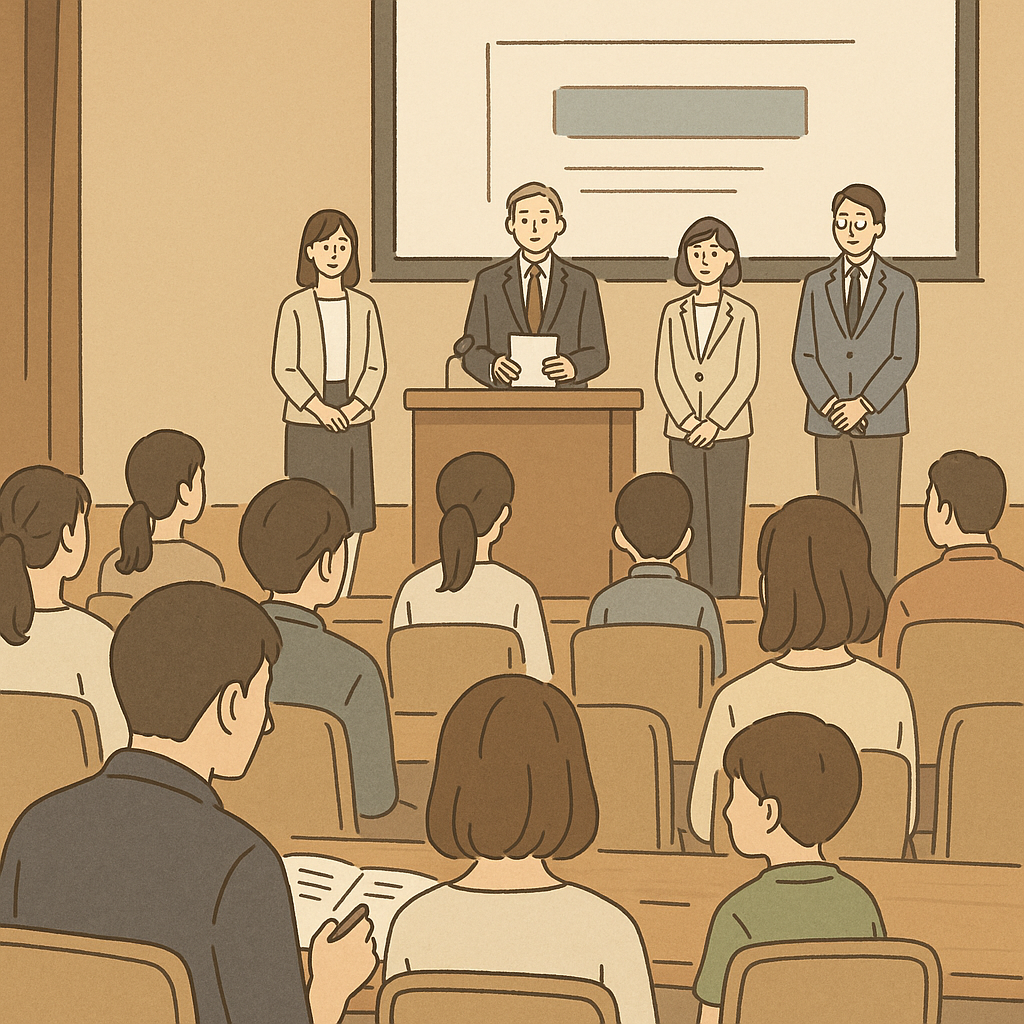

コメント