わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
偏差値更新の喜びと同時に見えた課題

9/6実施の公開模試で、4科合計の偏差値が過去最高の58.3に到達しました。
(これまでの最高は58.0)
まずは結果(偏差値)から。
・国 語:52.8
・算 数:63.2
・社 会:51.3
・理 科:62.1
・4科目:58.3
誤差の範囲と思う一方で、科目別の内訳と過去推移を並べると「一時的な上振れではなく、底上げの兆し」であることが見えてきます。
具体的には、算数と理科の安定得点が全体を引き上げ、国語・社会の取りこぼし縮小が総合偏差値の天井を押し上げました。点の伸びに一喜一憂せず、何ができて、何が未完かを言葉にしておきます。
一方で、今回の答案分析から特に算数、社会、国語の課題が浮き彫りになりました。
だからこそ、この最高値は課題が明確になったという意味でも価値があります。
成果の根拠と、残課題の輪郭を、体験ベースで深掘りします。
なかなか改善しない苦手分野
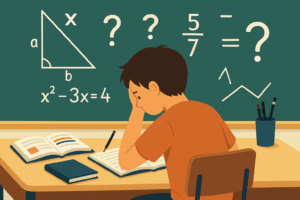
算数|図・線分図・軌跡――頭の中だけでは限界
「線分図を書かない」「図形の軌跡を描かない」――答案の余白はきれいでした。つまり、手が動いていない。難度の高くない設問で「あと一歩」の取りこぼしが続くのは、図示の欠落が原因です。思考の可視化がないまま頭内で組み立てると、途中で情報が蒸発します。今回も、ラスト5分の見直しで拾えるはずの1〜2問を拾い切れませんでした。
社会|輸入・貿易の“絡み”が曖昧
工業・農業ともに、海外からの輸入に絡む設問で失点。単発知識はあっても、「なぜ/どこの国から/どれくらい」という比率・因果が曖昧です。地図やグラフを伴う設問で詰まり、線で結べない知識が露呈しました。
国語|記述のハードルと語彙・慣用句
記述の難度が高かった一方、漢字・四字熟語・慣用句での落ちが痛手に。読みはできるが、書けない・運用できないという典型パターンです。設問文の要求(誰が/何を/なぜ)を1文で取り切れず、主語・述語のねじれが採点を落としています。
全国共通の流れと、模試で“今”意識すべき観点

ここで一歩引いて、全国的な教育環境の流れと模試活用の視点を整理してみます。
2025年度の首都圏中学受験率は27.2%に達し、4人に1人以上が挑む時代に突入しました。
【出典】https://resemom.jp/article/2025/06/25/82370.html
リセマム|【中学受験2026】「学校の真の姿」の見極め方…四谷大塚が教える学校選びのコツ
かつては一部の層に限られていた受験が、多様な家庭に広がっています。
模試の意味合いも「単なる偏差値測定」から「学校選びの軸を見極める材料」へ変化しています。
リセマムの記事では、学校選びにおいて「偏差値以外の観点が重視される流れ」が強まっていると指摘されています。
具体的には、教育内容や時代対応力を評価する動きが顕著で、大妻多摩の生徒主導による講演会企画や、富士見の投資教育導入、聖徳学園のデータサイエンスコース新設など、多様な事例が挙げられています。
こうした背景を踏まえると、模試で意識すべきは「得点や偏差値だけで志望校を絞るのではなく、学校が提供する学習環境や支援体制を見極める材料にする」ことです。
特に教育DXや探究学習、ポートフォリオ評価といった全国的に共通する潮流は、どの学校でも説明されるべき要素です。説明されなかった場合、それは学校独自の事情か遅れかを判断する手がかりになる。逆に、模試結果から弱点を把握し、それを説明会での質問に結びつければ、「わが子にこの学校は合うか」をより具体的に判断できます。
科目別:次の1カ月で“効く”処方箋(ミニ習慣)

算数|「描けば解ける」を習慣化する
- 毎日10分・線分図ドリル:割合・比・旅人算を「式の前に図」。書いた線分図をスマホで撮り、週1で5枚だけ見直す。
- 軌跡は3色ペン:条件ごとに色を変えて作図→色の切替=条件の切替を身体で覚える。
- 見直しの型:「答→式→図」の逆流チェックをラスト3分に固定。
社会|地図・グラフ→1行因果
- 地図×品目×相手国の3点メモ:品目・相手国・理由を1行で。例:「大豆→米:広大・機械化」。
- 週1の貿易ミニテスト:トップ3輸入国・輸入割合・代替品を3問×5分。
- 白地図“1分書き足し”:食料・資源・工業製品を日替わりで1アイコンだけ追加。
国語|記述の骨格+語彙は“5分×3”
- 1文要約ドリル:設問文に「誰が/何を/なぜ」をカッコで先に書いてから本文へ。
- 語彙は10語×アクティブリコール:意味→例文を口で言ってから書く。書く前に言う。
- 記述テンプレ:「理由はAだから」「筆者はBと考える。根拠はCだ」の二段で練習。
最高偏差値の“意味”を取り違えない:3つの合図

- 合図1=正答率50%超の取りこぼしが減った:これは型が定着してきた証拠。次は「図示の初動」をさらに前倒しに。
- 合図2=誤答タグが共通化した:同じ論点で間違える=根治対象が見えた。治療計画を週次に落とす。
- 合図3=“運の点”が減った:大問の選択と撤退判断が冷静に。見直しの逆流チェックが効いているサイン。
明日から動ける“3アクション”

- 24hリライト:模試誤答のうち3題だけ、翌日までに「なぜ」で1行メモ→同類問題を1題だけ追加演習。
- 図示の仕掛け化:線分図・作図のチェック欄付き台紙を印刷(A4一枚)。式より先に✓。
- 週1・貿易ミニテスト:輸入品目3つ×相手国×理由を5分で。家族も参加OKのクイズ形式で回す。
最高偏差値の更新に一喜一憂せず、まずは来週の育成テストに取り組みたいと思います。



コメント