わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
小5後期は「壁」と「伸び」が同時に訪れる時期

秋に入って、日能研のカリキュラムが明らかにギアアップしました。
算数は比・速さ・立体図形。社会は地理から歴史に切り替わり、覚えるだけでは太刀打ちできない「理解して、つなげる力」が求められてきた印象です。
加えて、週末テストや宿題の量もぐっと増えました。
冬期講習の予定まで見えてきて、「これは確かに、負荷が一気に上がるな…」と、正直ひるみました。
親としては、「この量に耐えられるかな」「これで勉強嫌いになったりしないかな」と不安になる場面が多くなりました。
でも、そんな負荷の中に、息子が以前よりも粘って考えたり、説明の精度が上がったりする様子が見られて、「壁と伸びって、同時に来るんだな」と気づかされたんです。
テキストを開いて気づいた、小さな工夫と広がり

後期のテキストを初めて見たとき、最初は「量がすごい…」と気圧されました。
でもよく見ると、漫画が差し込まれていたり、扉ページにちょっとしたイラストや問いかけがあったりして、「お、ちょっと面白そう」と思わせる工夫が散りばめられているんですよね。
特に印象的だったのは、教科をまたいだ連動感。
ある日の国語で出てきた人物が、社会でも登場して「今日はリンクしてたね」と親子で話せることもありました。
そういう小さな発見が、本人の中で「これは覚えるだけじゃなくて、つながってる」と気づくきっかけになるのかもしれません。
うちでは、そういうつながりを見つけたときに「へぇ〜そうなんだ!」とちょっと大げさにリアクションしてあげるようにしています(笑)。
最近の流れと教科ごとの“つまずきどころ”ヒント
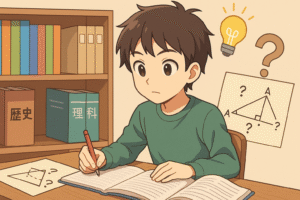
最近の学校教育は国全体として「思考力」や「表現力」を重視する方向にどんどん進んでいるそうです。
探究学習とか、生成AIとか、そういうワードもよく聞くようになってきました。
小5後期になって、記述問題や説明の比重が増えてきたのは、塾だけの方針じゃなくて、国の流れとシンクロしているんだなと後で納得しました。
教科別に見ても、「これは今の息子にとって負荷が大きいな…」と感じる部分ははっきりしてきています
算数
- 比・速さ・立体図形など、受験頻出かつ思考力を問われる単元が集中。
- 「線分図を書かない」「手を動かさない」ことが課題になりがち。図や図形を描く習慣をつけることが最優先。
国語
- 論説文・物語文の難度が上昇し、詩歌も登場。
- 記述式はレベルが高く、書き慣れていない子にはハードルが高い。
- 漢字・四字熟語・慣用句の取りこぼしは偏差値に直結。基礎知識の網羅性が求められる。
理科・社会
- 記述問題が増加し、単なる暗記から「説明できる」ことへシフト。
- 社会は歴史分野に入り、流れや因果を理解させる学習が中心に。
- 理科は観察・実験を前提にした問題が多く、背景を語れる力が必要。
こうやって見ると、どこでつまずきそうかが、かなり具体的に見えるようになってきたなと感じています。
成績が上がったときほど、「その裏で何が定着してないか」を丁寧に見るようにしています(ときどき見逃しますけど…)。
我が家がやっている、今すぐできる3つのサポート
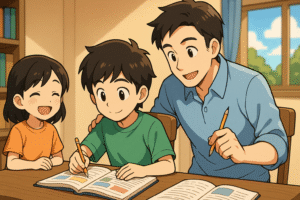
最後に、明日からすぐ取り入れられる3つの具体的なアクションを提案します。
① アウトプット習慣を作る
「今日、何やったか教えて〜」と声をかけてみるだけ。
社会の出来事でも、算数の考え方でも、説明してもらうと理解の深さがよく分かります。
本人も「説明できる=わかってる」と感じられるみたいで、ちょっと得意げになります。
② 図を描くルールを決める
算数では「文章題を読んだら、必ず線分図を描く」という約束をしています。
正直、最初は面倒くさがってましたが、図を描くことでケアレスミスが減ってきました。
③ テスト直前に振り返り時間をとる
日頃の宿題から間違えた箇所は赤字で☑️をして、青字で正しい解答を記載することを徹底します。
テスト直前に見返す内容を自分が間違えたことに集中することで同じ間違えを繰り返さなくなるといいなと考えています。
まとめ:一緒に迷いながら、でも前には進めている気がします
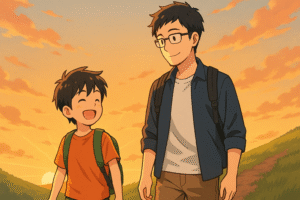
小5後期は、これまでの「勉強」から、「受験」を意識するようになる大きな転機です。
親の私も、「いよいよ来たか…」と内心ドキドキしています。
でも、教材の中に散りばめられた工夫や、子どもの小さな変化を見逃さずに拾っていくと、
この時期だからこそ味わえる“手応え”があるのかなと最近は感じています。
できるようになったこと、できないこと、どちらも一緒に見つめながら。
一歩ずつ、でも確実に進んでるんだなと、信じられるようになってきました。
焦らず、構えすぎず、「わが家なりのペース」で乗り越えていけたらと思っています。


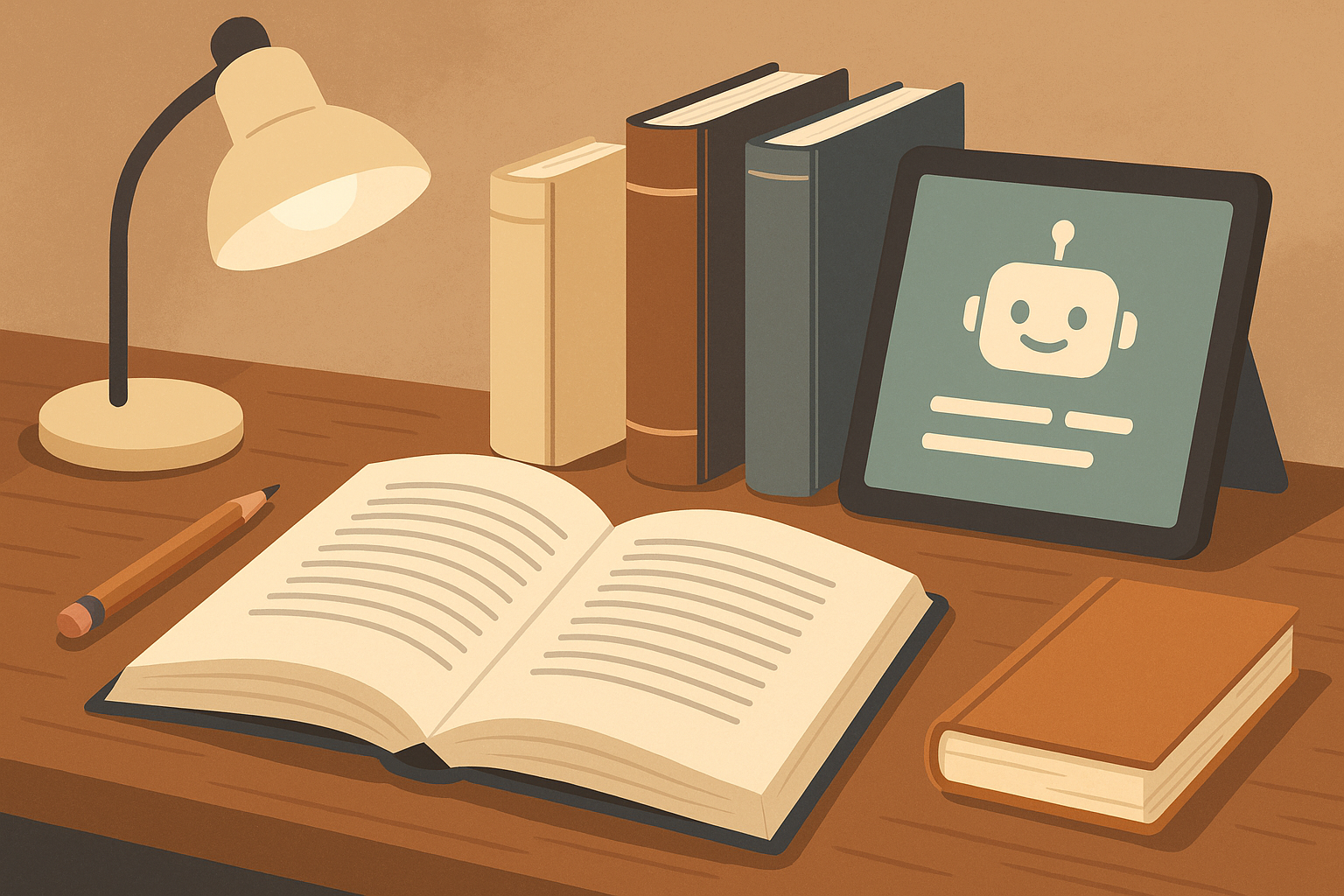
コメント