わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
「読書は大事」とは思いつつも…
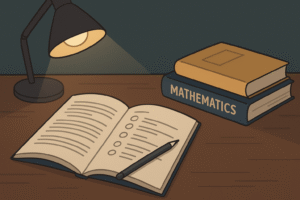
国語の成績が安定しない。読解問題に手応えを感じにくい。
——これは、わが家の長男の中学受験勉強において、ずっと抱えている悩みのひとつです。
算数や理科は「理解→演習→定着」のサイクルが比較的見えやすい一方で、国語は“何をどう積み上げればいいのか”がつかみにくい。
模試の記述で減点されても、「なぜ?」と聞かれると答えに詰まってしまうことも多く、親としてももどかしさを感じてきました。
そんな中で最近、とある教材の話題が目に留まりました。
「読書が増える」と聞いて気になった教材
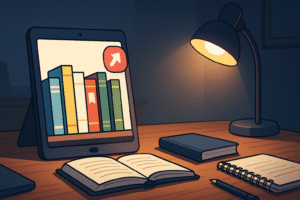
目にしたのは、「ヨンデミー」という読書支援アプリ。
2025年5月から、中学受験専門塾「伸学会」の小学6年生の1クラスで実証実験が行われ、わずか1ヶ月で平均読書量が週3冊を超えたというニュースでした。
【出典】PRTIMES「ヨンデミー、中学受験塾に導入1ヶ月で小学6年生の読書量が週3冊超に増加!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000071742.html
え? 週3冊って、本当に?
それが第一印象でした。
わが家でも読書の重要性は頭ではわかっているつもりで、「できれば読んでほしいな」と思いつつ、日々の塾・宿題・復習の中で読書の時間はどんどん削られていくのが現実です。
ただ、このヨンデミーの特徴を見ていくと、単なる「読書管理アプリ」ではなさそうだということがわかってきました。
AIが“今の子どもに合った本”を選んでくれる
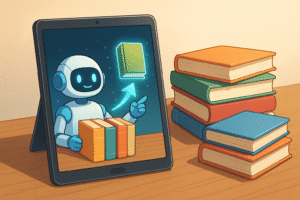
ヨンデミーの大きな特徴は、「AIによる選書」です。
子どもの年齢や読書履歴、好みのジャンルなどをもとに、本の難易度・テーマを調整しながら、その子にぴったりの本を個別に提案してくれるというもの。
さらに、以下のような工夫が施されているそうです:
- 読書感想を共有できるSNS機能(「本の友」)
→ 同じ本を読んだ子同士や先生と感想をやりとりできる - レベルアップ要素があるゲーム感覚のUI
→ 「〇〇冊読んだら◯級に昇格!」など子どものモチベを刺激 - 家庭学習や通学時間にも対応
→ スキマ時間に読書習慣を作るためのリマインドやミニレッスンがついている
実証実験に参加した塾では、読書量が明らかに増えただけでなく、国語の記述問題への取り組み方や文章への姿勢にも変化が出たという声が上がっているとのこと。
実際に導入したわけではないけれど…
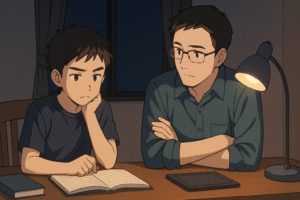
調べてはみたのものの、我が家ではまだこのヨンデミーを導入していません。
ただ、「もし今、国語を伸ばすために“根っこ”の部分を見直すなら、こういう取り組みが選択肢に入るかも」と感じたのは確かです。
わたし自身、中学受験で全落ちした経験があるからこそ、「点数や偏差値」だけでなく、「自分の考えを読む・伝える・つなぐ」力の大切さを痛感しています。
その力はすぐには身につかない。でも、読書を通じてじわじわと育っていくものだと信じたい。
ヨンデミーのような仕組みがあることで、ただ“本を読む”だけではなく、「誰かと感想を共有しながら読む」「自分の言葉で書いてみる」という経験につながるなら、それは国語の学習にとっても大きな土台になるのでは…と感じました。
わが家なりに今できること
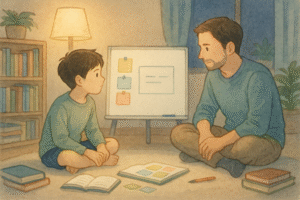
今のところ、長男には紙の読書記録ノートを手渡して、「面白かったページに付箋を貼っておいて」と伝えています。
SNSやアプリを使わなくても、“読んだものを何らかの形で残す”ことを意識してもらうだけでも、少し読書の見え方が変わるかなと思ったからです。
あと、意識しているのは「親が読んでる姿を見せること」。
仕事の合間にKindleで読書しているだけですが、長男が「何読んでるの?」と聞いてきたこともあり、ちょっとした連鎖反応のようなものを感じています。
「読む力」をあらためて考えてみるきっかけに
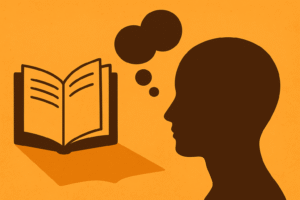
中学受験を意識すると、「読書=非効率」と思ってしまう時期がどうしてもあります。
でも、今回ヨンデミーの実証実験を見て感じたのは、読書は勉強と別物ではなく、むしろ“つながっている”ということです。
- 自分に合った本と出会う体験
- 感想を言葉にする体験
- 誰かと共感し合える体験
こうした読書の積み重ねが、国語の「読み取る力」や「記述で自分の意見を書く力」にじんわり影響を与えていくのだとしたら。
無理に詰め込むのではなく、楽しく続けられる仕組みの中で“読む力”を育てることは、これからの時代にとても価値があるのかもしれません。
まとめ:今はまだ“気になっている段階”だけれど
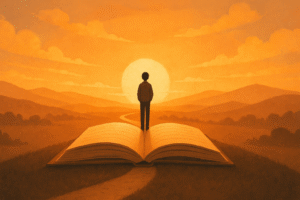
ヨンデミーという教材について「こんな取り組みがあるんだ」と知り、気になったので自分なりに調べてみました。
実際に導入していないからこそ、「うちはこう考えている」「こんな疑問がある」というスタンスで冷静に眺めることができましたし、今後の国語の伸ばし方を家庭でどう位置づけるかを考えるきっかけにもなりました。
もし読者の方で、「うちは導入してみた」「こんな工夫をしている」などの体験があれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。
わが家では、少しずつ“読むこと”の優先順位を上げる準備をしているところです。
その過程も、またこのブログで記録していけたらと思います。
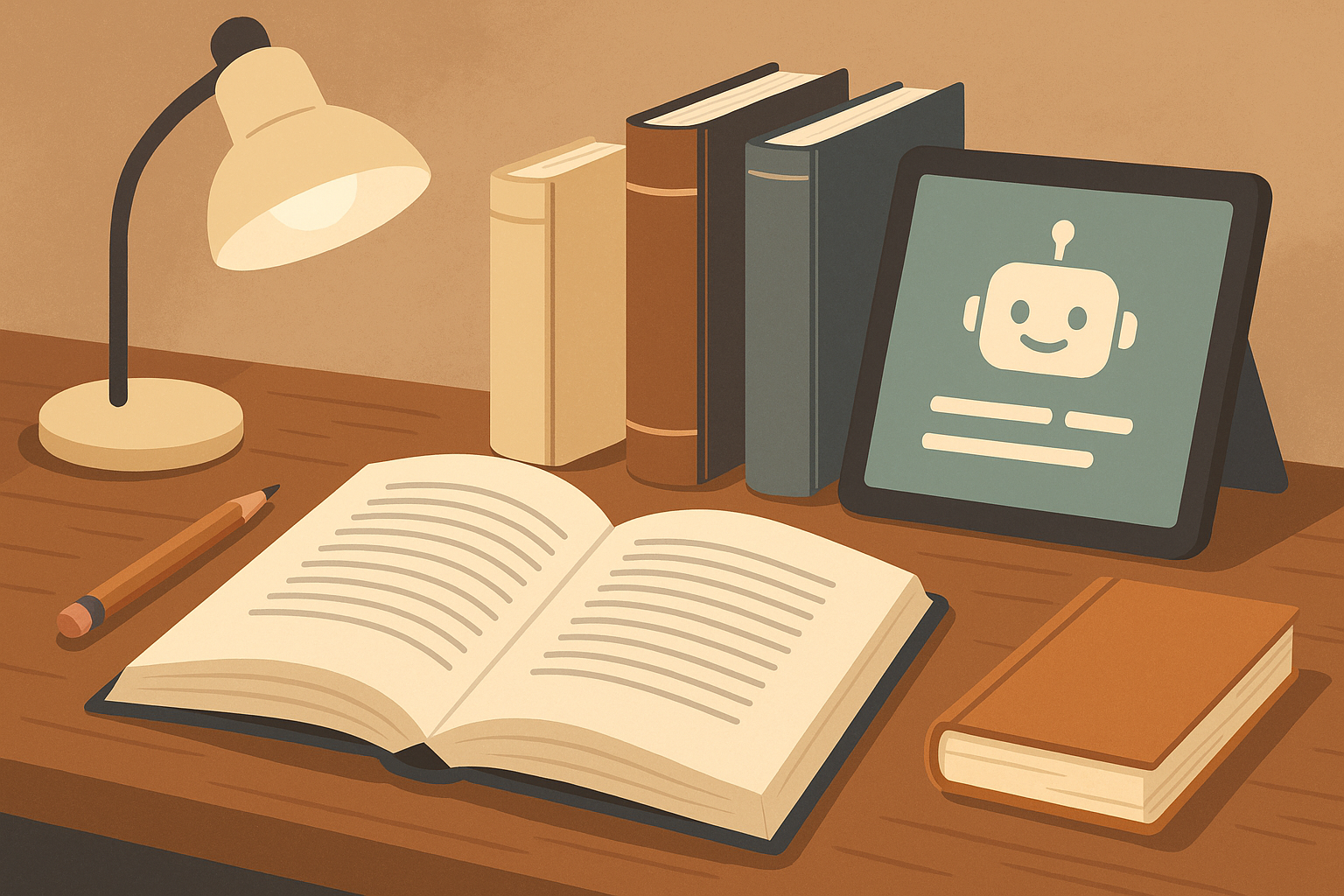


コメント