楽しみながら学習習慣が身につかないだろうか?
長男が4歳の時、夫婦で色々調べ始めてぶつかった問いでした。
情報があふれる今、何から始めればよいのか迷うご家庭も多いのではないでしょうか。
こんにちは。40代会社員であり、2027年に中学受験を予定している長男(小5)と、長女(小1)を育てる父親です。
共働き家庭として日々の時間捻出に苦戦しつつも、我が子の成長に少しでも伴走できるように模索を続けています。
私自身のことや家庭の状況はこちらで紹介しています:
▶ 自己紹介はこちら
この記事では、共働き家庭である我が家が、長男の成長段階に応じて選んできた学びの選択肢 ――こどもちゃれんじ、スマイルゼミ、そして日能研――を紹介します。
小さな習慣がやがて大きな力になるプロセスを、リアルな体験を交えてお伝えします。
こどもちゃれんじで学びの楽しさを知る
長男が4歳のときから「こどもちゃれんじ」を始めました。
紙の教材が中心で、工作が好きな長男はすぐにハマりました。
祖父母の家に教材を届ける選択もでき、根気強く一緒に取り組んでくれました。
また、簡易的なタブレットを使って、しまじろうと一緒に学ぶスタイルは親しみやすく、学ぶことへの抵抗感を和らげてくれました。
ひらがな、数、時計の読み方といった基礎を楽しく身につけられたことで、「学ぶって楽しい!」という感覚を育てられたのは、今でも正解だったと思っています。
スマイルゼミへの移行と習慣化の強化
小学校に入学後、小学校の授業進度に合わせたカリキュラムに魅力を感じ、「スマイルゼミ」に移行しました。
音声ナビや自動丸つけ、視覚的なわかりやすさが子どものモチベーション維持につながりました。
特に「今日のミッション」や「連続学習記録」など、ゲーム感覚で継続的に取り組めました。
スマイルゼミを小学3年の1月まで続ける中で、多少の波はありましたが、日々の生活に“学び”を組み込むことに抵抗のない姿勢が育まれていきました。
中学受験を意識して塾を検討
小学3年生になり、中学受験を見据えて学習塾の検討を始めました。
我が家が日能研を選んだ理由については別記事に詳細を綴っています。ここでは通信教育から塾への移行において感じたギャップと気づきを共有します。
塾に通い始めてからの変化と気づき
日能研に入ると、それまでの家庭学習とのギャップに驚きました。
国語の読解では長くて今まで読んだことのない文章を読むことに慣れるまで時間がかかり、設問形式にも戸惑いました。
算数では「考え方の筋道」を求められ、ただ答えを出すだけでは通用しません。
今思えば、学ぶことの抵抗感をなくすことと中学受験の学習は似て非なるところがありました。
しかし、スマイルゼミで身につけた自学自習の姿勢――自ら教材を開く習慣、取り組みの記録、達成感の体感――は通塾後も確実に生きています。
また、日能研では定期的な保護者会や個別面談があり、子どもの理解度や取り組み姿勢について詳しいフィードバックが受けられます。日能研の個別面談の詳細については実体験を交えてこちらの記事にまとめています
家庭での子どもの様子と照らし合わせ、どう支援していくかを話し合える環境も重要だと感じました。
こどもちゃれんじ・スマイルゼミが共働き家庭に合っていた理由
- 誰がサポートしても同水準の成果が得られる(こどもちゃれんじ)
子どもが勉強や学びを好きになるか嫌いになるかは”教えるのが誰か”に依存することが大きいのではないでしょうか。
好きな先生の教科が好きになり、勉強時間が増え、結果的に成績も伸びるといった経験をしたことがある方は少なくないと思います。
こどもちゃれんじを始めるにあたって注意を払ったのは、長男が誰と取り組んでも楽しめるということでした。
例えば、「パパは間違えるとすぐ怒るから一緒にやりたくない」とか「ママは一緒に始めてもご飯作ったりスマホ触ったり別のことするからつまらない」といったことにならないように夫婦で話し合いました。
また、祖父母の世代は我々と異なった教育観を持っていることが多くあります。
ましてや、孫に対する教育の責任感と子供に対するそれは違って当然です。
祖父母側も孫の教育にどこまで口を出していいのか迷うこともあるかと思います。
こどもちゃれんじの教材が素晴らしいと感じたのは教えるのではなく見守ることで作り上げられたり、問題を解くことができる点でした。
このことは共働きの我が家にとってストレスを感じることなく、続けることに繋がったと思っています。 - 自動丸つけ機能で子どもが完結できる(スマイルゼミ)
ヒント機能や正誤フィードバックにより、子どもが自立して進めやすく、親は進捗を把握するだけで済みます。丸つけは負担に感じる方が多いのではないでしょうか。
とはいえ、やりっぱなしで間違った理解のままになってしまうのも危険です。
スマイルゼミは一問ごとに正解・不正解を判定して、不正解の場合は先に進めない問題もありました。
不正解が続く場合はヒントを出して正解に誘導してくれますので子どもが分からなくて親に聞いたり、嫌になって投げ出すことは我が家の場合ありませんでした。
正答率や分野別の得意不得意が親にフィードバックされて一目で分かる機能によって、子どもは自己完結していると感じさせながら、親は取り組み状況を把握することができました。 - 学力以外の知恵や経験につながる教材の提供
プログラミング、工作、家庭菜園など多様な体験が可能で、学びの興味・関心の幅を広げてくれました。我が家の場合、夫婦の学力から推察して子どもの学力に高望みしていませんw
親と子どもの学力にどこまで相関関係があるのかと言った専門的なことはわかりませんが、平凡な夫婦である私たちは学力以外の生きる知識・経験を子どもに得てほしいと願っています。
シンプルに子どもが興味・関心を惹かれる領域を広く散りばめて、何かヒットすればいいなと思っている程度です。
両ツールを利用してプログラミングをして自分でゲームを作ったこと、折り紙や粘土遊びから今では親の誕生日に手紙を書いたり、オリジナルの人形を作ってプレゼントしてくれたこと、きゅうりを育てたことで種を土に撒いて水をやり、太陽を浴びることでどんどん成長して実がなることを体験できたことは貴重な経験だったと思っています。
通信教育と塾、両方を経験したからこそ見えたこと
通信教材は子どもに合ったペースで進められる反面、塾では「時間内に解く」スキルが求められます。
しかし、家庭での“自律的な学び”の経験があったからこそ、その壁を乗り越える準備が整っていました。
子ども自身も「正解するためにどうすればいいか」を自ら考えるようになり、学ぶ意識に変化が表れました。
最後に:小さな一歩が未来につながる
「スマイルゼミで足りるのか?」「いつ塾に入れるべきか?」
答えのない問いに、唯一言えるのは「まず始めてみること」。
こどもちゃれんじを申し込んでみる、スマイルゼミの体験版を試してみる、どんなことでも始めてみなければ我が子に合っているかどうかは分かりません。
家庭学習から塾へのステップは、決して遠回りではないと思っています。
わが家のように段階を踏んで学びの土台を築く方法も、十分に有効ではないでしょうか。
ぜひ、お子さん自ら学ぶ姿勢や習慣が身につけられる教材やツールに出会われることを願っています。
※こどもちゃれんじやスマイルゼミの資料請求・体験版も、まずは一歩としておすすめです。
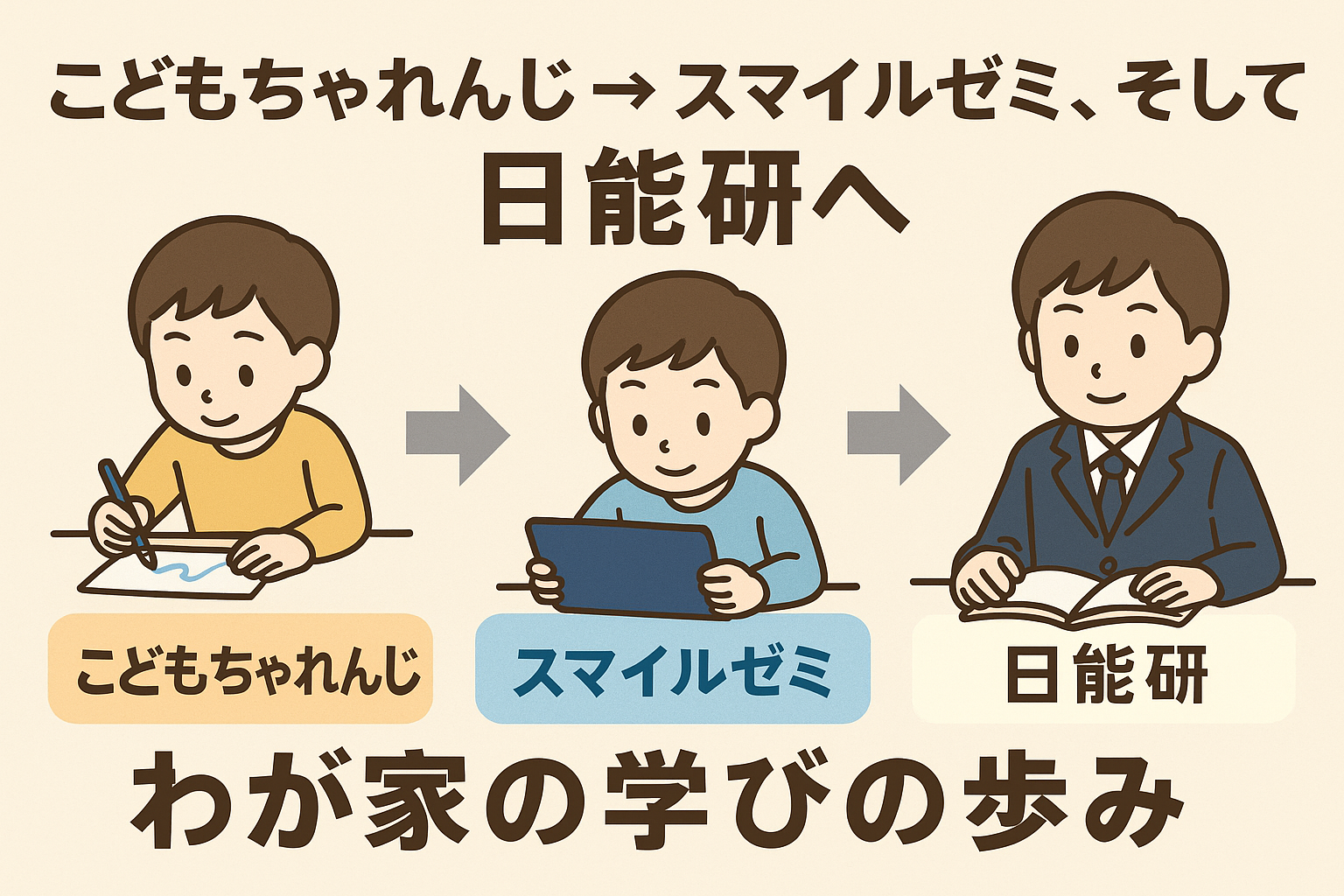
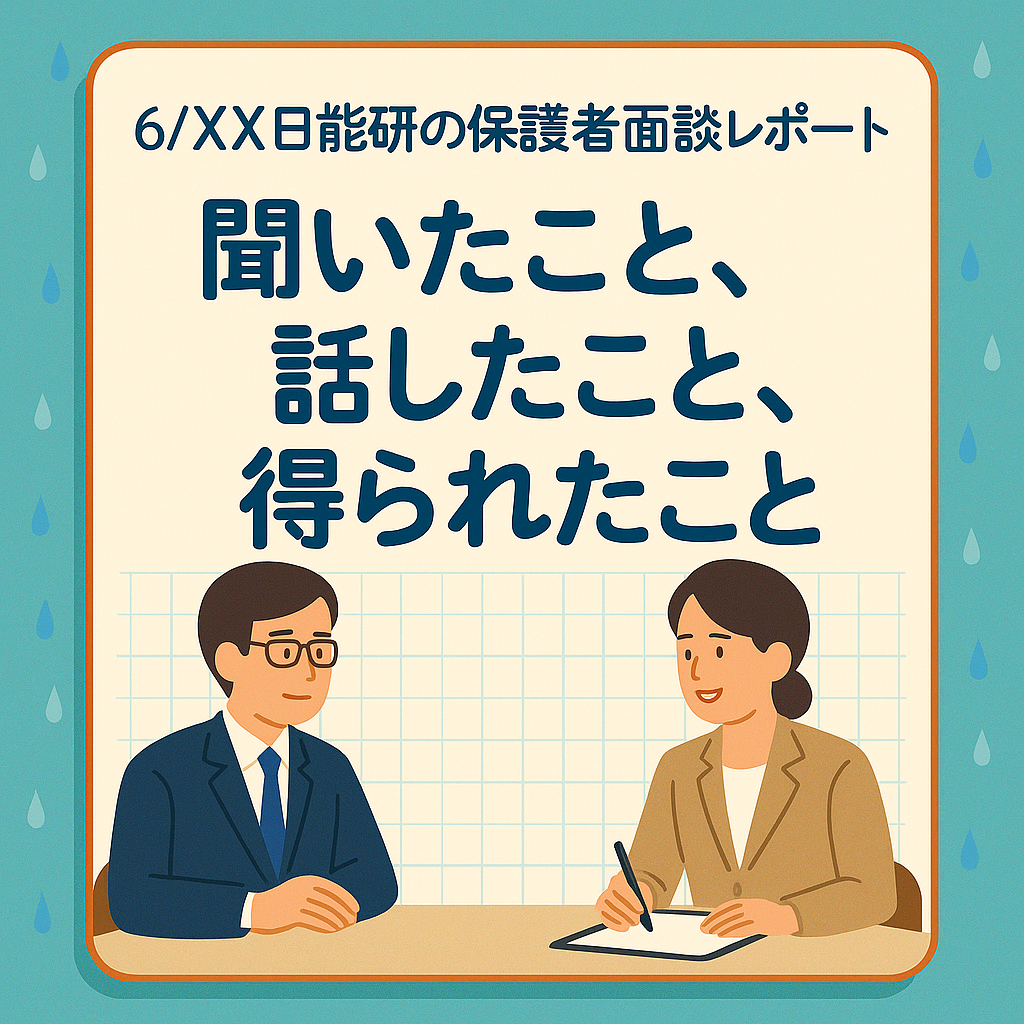

コメント