「うちの子、中学受験を考えているけど、塾は何年生から始めればいい?」
「共働きで忙しいから、送り迎えや家庭での学習サポートが不安…」
そんな悩みを抱えているご家庭も多いですよね。
実際の調査では、難関校に合格した子どもが最も多く塾を始めるのは『小学4年生の2月』です。でも約20%の子は、塾なしで合格しています。
こんにちは。40代の会社員であり、2児(小5長男、小1長女)の父です。
このブログでは、長男(2027年受験組)の中学受験に伴走する父親目線の勉強のサポートや塾のこと、親としての喜怒哀楽などを綴っています。
同じく受験を控えるご家庭と情報を共有できればと思います。
私自身のことや家庭の状況はこちらで紹介しています:
▶ 自己紹介はこちら
この記事では、小3の2月から日能研に通い始めた際に検討した最適な塾スタート時期をお伝えします。
❶ 中学受験の塾は何年生からが一般的?
中学受験で人気の大手進学塾(日能研、早稲田アカデミー、SAPIX、四谷大塚)は、『小学4年生の2月』スタートが主流です。
最近では、早期に『小学3年生の2月』から通塾する家庭も増えています。
❷ 【調査データ】塾スタート時期と合格率の関係
全国の偏差値60以上の中学校に合格した子ども150人の調査結果を調べてみました。
| 📊 塾を始めた時期 | 📌 割合 |
|---|---|
| 小学4年生の2月~5年生の1月 | 23.3% |
| 小学3年生の2月~4年生の1月 | 22.0% |
| 通塾なし(家庭学習のみ) | 20.7% |
| 小学5年生の2月以降 | 19.3% |
| 小学1年生から | 4.0% |
(出典元:「中学受験塾に通い出したのは何年生から?」全国偏差値60以上の中学校に通う保護者調査|ひまわり教育研究センター, 2022年調査)
地域別では関東が小学4年生の2月スタート最多、近畿では通塾なしや遅めスタートが多い傾向です。
❸ 塾スタート時期別メリット・デメリット【筆者の体験談あり】
🔹 小学3年生スタートの場合
メリット
• 基礎学力をしっかり養える
• 学習習慣が早めに定着
• 余裕を持った学習が可能
デメリット
• 長期化によるモチベーション維持の難しさ
• 費用が年間約50〜100万円増える
• 親の送迎負担が増える
🖋️ 筆者の体験談
「長男が小3の2月に日能研に通い始めましたが、最初の半年(2月〜7月)は授業が終わる19時30分頃に一人で帰宅させるのが心配だったので毎回迎えに行きました。そのため在宅勤務を増やしたり、祖父母の協力を得るなどの調整をしました。在宅勤務をしていても18時頃には仕事を切り上げ、長女のお風呂、夕飯の準備をしたら19時過ぎに長男を迎えに行くとサイクルは初めは負担に感じました」
🔸 小学4年生スタートの場合
メリット
• 塾の本格的なカリキュラムが始まるベストタイミング
• 同時期に通う子どもが多く情報共有しやすい
• 負担が適度で効率的
デメリット
• 先行組との差を感じる可能性あり
• 学習習慣がないと定着が難しい
❹ 共働き家庭のリアルな日能研通塾スケジュール
実際に筆者の家庭で実践した通塾スケジュールをご紹介します。
| ⏰ 時間 | 🎒 子ども | 💼 親の対応 |
|---|---|---|
| ~16:00 | 学校終了 | 在宅勤務や早退調整 |
| 16:30 | 日能研へ送迎 | 勤務終了調整 |
| 17:00〜19:30 | 授業 | 家事や仕事の残務 |
| 19:30 | 帰宅 | お迎え |
| 20:00〜 | 夕食・家庭学習 | 親がサポート |
❺ 我が家に最適な塾の開始時期【セルフチェック】
🔷 学習習慣が身についている
🔷 基礎学力が十分ある
🔷 送迎体制に自信がある
▶︎ 全て当てはまれば『小学3年生2月』スタートを推奨
🔶 子どもがまだ遊びたい
🔶 学習習慣がない
🔶 送迎が不安
▶︎ 一つでも当てはまれば『小学4年生以降』スタートが適しています。
❻ まとめ:結局、日能研は何年生から通うべき?
🔷 一般的には『3年生後半~4年生前半』が最適
🔷 塾に通うことに向いているのか経験させてみないと分からないのでまずは通ってみるのも手
🔷 送迎や家庭の事情を踏まえ、適切な時期を選ぶのがベスト
❼ 日能研の無料体験授業を活用しよう
まずは日能研の無料体験授業を試してみてください。実際の雰囲気やサポート体制を確認できます。
- ▶ 日能研|入会前に体験授業を受けたい方はこちら
【他塾と比較したい方向け】 - ▶ SAPIX|入室テストの詳細・申込はこちら
- ▶ 四谷大塚|1週間無料体験カリキュラムを試してみる
- ▶ 早稲田アカデミー|体験授業・入塾の流れを確認する


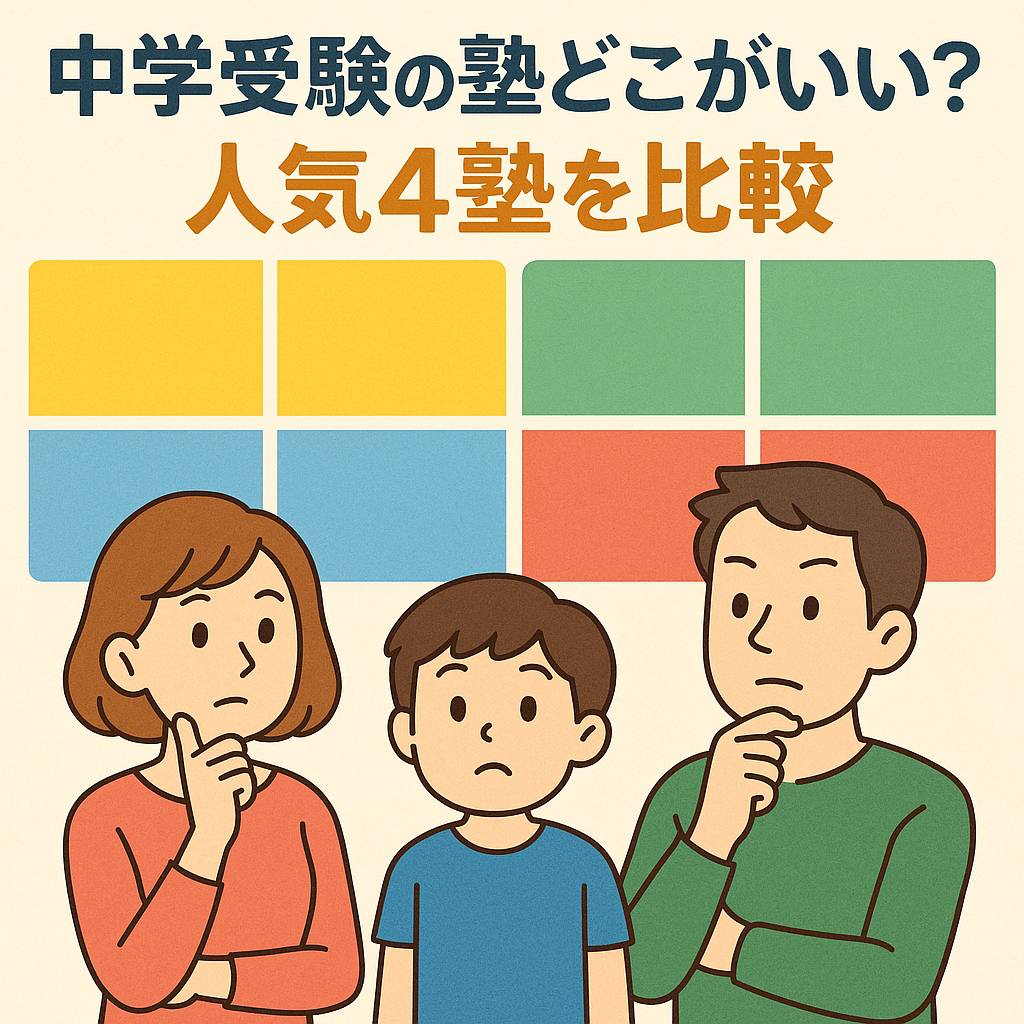
コメント